懐かしい友だち
めずらしく家の電話が鳴りました。我が家の電話は迷惑な電話がかかることががあるので、居ても留守電になっています。たぶん、いつものようにすぐに切れるだろうと思ってました。けど、その人は留守電に話している。あれ!岐阜なまりの話し方、すごく懐かしい感じ、友達だ!と急いで受話器を取りました。
あれから15年だろうか、ずっと会ってない高校時代の親友でした。母と伯母が実家を離れた後、行くことがなくなった岐阜、いつの間にか連絡先もわからなくなって、最近、気になっていた友達でした。
彼女も連絡するのに携帯の番号もわからなくなっているし、なんとか見つけた電話番号にかけてみたんだそうです。嬉しかったです。お互いに姿が見えないから、15年経った顔ではなく、15年前の姿を描きながら話しました。(笑)
その後のことをお互いに話して、長電話になりました。まだまだ話すことが山ほどあるんだけど、今はコロナで会うことができない。コロナが終息したら、きっと会うことができると受話器を置きました。
50年前のふたり
彼女の人生は苦労の連続でした。なので今、15年前よりもずっと落ち着いた日々を過ごしているのがわかって安堵しました。とにかく電話してくれたのが嬉しかったです。
ありがとう!
家から出ない生活を続けていると、いつもは時間がなくて出来ないでいる大事なことに目がいきます。この7年、ゆっくりと自分のことを考える暇がない上に、海外に居るなど、居場所が安定しない生活だったので毎年の年賀状も書けなくて、多くの友人と連絡ができなくなってしまいました。
家で過ごす毎日、少しづつですが、私自身の大切なものを確認していく日々にしていきたいと思った日でした。
盆踊り
岐阜県郡上市八幡町の盆踊り、50年以上前から有名でした。私が育った美濃太田でも当時は盆踊りが盛んでした。その時代でも郡上八幡での徹夜踊りに行くのは若者たちの楽しみで、うちに住み込みだった若い看護婦(当時はこう呼ばれてました)さん達は仕事が終わると出かけて行って、朝になって帰って来てました。当時、美濃太田の盆は23~ 25日でした。郡上八幡は13~16日なのです。
私は踊りであれば、なんでも好きなんですが、今にも至るまで郡上八幡に行ったことがありません。5年前の夏だったと思うのですが、岐阜から飛騨、立山への一人旅を企画した時に郡上八幡近くの宿を探したのですが、満室で取ることができずに諦めました。いつか、訪れたいと思っているのですが。今年はコロナが阻んでます。
昨日のTV「新日本風土記」は郡上八幡でした。それは私の子ども時代から青春時代の再現のようでした。盆踊りの踊りも歌も盛り上がりも全く同じでした。私も、中学高校時代、大学から帰省時もやはり踊り続けて朝帰りでした。
故郷、美濃太田は郡上八幡のような昔からの町並みは旧街道(中山道)で、活気があったのは駅からの木曽川までの大きな通りでした。なので、出し車は郡上八幡よりも大きかったように思いましたが、20時頃から始まって明け方まで踊るのは同じでした。その日だけは学校も夜中に出ることを黙認でした。
この写真はTVからの画面です。
盆踊りの曲は「かわさき」「さば(春駒)」「炭坑節」「東京音頭」などなどでした。上の写真の「アソンレンセ」という歌詞は「かわさき」です。全国区というか、有名な盆踊りの曲が流れてました。
三味線、太鼓、笛、唄を歌う人が乗って演奏されてます。
美濃太田では囃子の楽器を演奏するのは芸妓さん達でした。出し車は確か二、三台、唄を歌うのは男性でした。その歌う声と囃子は何個かの拡声器から流れてました。踊りがピークに達すると踊りの輪は1㎞往復の輪になるだけでなく、それが三重の輪となります。賑やかでした。
これはTVの画面ですが、このような輪ができていました。
昔の写真を探せば、たぶん残っているだろうと思うのですが・・・
懐かしくて、わくわくする日々を思い出しました。
ブルーベリー
網をかけたブルーベリー、それでも鳥は来た!しぶとい!
イソヒヨドリの雄、ブルーでオレンジの鳥が外で歌っている。網がかかっていても気にしないのか、他の木に隠れるように近寄る。塀にかかるように枝が伸びている実を狙っているようだ。そこには網が掛かっていない。
私の姿を察知すると飛び立つ。そして上の電線にとまって、警戒するような鳴き声を発している。それは私に対してなのか、他の鳥に対しての威嚇なのかはわからない。
諦めたのかと思ってると庭に侵入者の影を感じる。やはり懲りずに枝に止まっている。この辺りは近くに山もあるし、そんなにブルーベリーにこだわることもないだろうに。
イソヒヨドリがこの地で確認されたのは今から30年以上前かと思う。イソという名前なので、海岸に近い場所に生息する鳥だと思っていたのだが、毎年、5月頃になると、美しい鳴き声の鳥が医院の煙突にやって来るようになった。なんという鳥なんだろうと思っていた時に友人のたじまもりさんにイソヒヨドリだろうと教えていただいた。
下の写真は2014年の8月20日頃に撮ってます。イソヒヨドリではなさそうですが・・
以来、毎年、来るようになって、いつのまにか増えて、あちこちで見かけるようになった。うちのご近所さん、庭がない家が多い。なので我が家の庭の実は彼らにとって好物なんだろう。私が留守がちだったのでここは自分の庭だと思っているのかもしれない。
写真を撮ろうとするのだけで気配を察して逃げるので撮ることができない。
今年は実を食べたいと言ってる孫のために網掛けしました。黒くなった実をひとまず収穫しました。まだまだ色づいていない実があります。イソヒヨドリは諦めるだろうか?
そして・・・
朝から暑い日でした。外の風を入れているけど、昨日のような爽やかさはない。湿った空気でした。
9時過ぎにエアコンの設置工事の人が来ました。前の室外機の位置を確認して、隠蔽配管になっていると言われる。真下に降りてても、通っている壁が入り組んでて簡単にはいかないと思っていたのでこれを使わないでベランダに設置を頼みました。
二階の部屋の外にあるベランダに室外機を設置し、前のエアコンと室外機を外して下取りということで無事、終了しました。ホッ!
これで家の中に籠るしかない暑い夏を乗り切ることができます。エアコンをON、OFFすると「冷房を28度で開始します」「運転を停止します」と女性の声でアナウンスされます。
ふふふ、ひとりじゃなくなったね〜
さ〜て、じっくりと身体をほぐすことにします。
なぜか暖房!
私の部屋のエアコンをかけると、どう感じても暖房になっている。もしかしたらクリーニング出来てないからかもと取扱説明書を探す。ずいぶん見てないから、どこだろう?と思ったけど、たぶんここだろうと思った場所にありました。大丈夫!まだボケてない。(笑)
さて作業を始めると機種は間違っていないけど、図が少し違うので、どこのことを言っているのか、わかりにくい。老眼なのでメガネをかけて読んでるわけだけど、エアコンは高いところにつけてあるのでかなり苦戦しながら、何度も見ていると、そうか!ここのことだと気づいた。
そうなると作業は簡単で、分解し埃が溜まっていたユニットを掃除することが出来て、元に戻してホッとした。さて、これで解決したのだろうか?エアコンをつけてみる。
あ〜あ、暖房!!
このエアコン、2008年の製品だから、古いし、買換え時かなあ?!
それでも何か原因があるかもとリモコンの乾電池を取りかえてみた。で、始動!・・・やはり、暖房!これ以上は素人では無理です。
ということで結局、買い換えることにしました。(泣)
8月6日11時の室温です。今日は35度以上になるという予報です。
「はい!場所は二階で、ベランダに室外機があります。」と言って新エアコンを買い、設置の予約をして帰りました。帰ってしばらくして、ベランダに出てみました。あれっ、室外機がないじゃない。
配管は壁に入って・・・その先がどこに行ったのか?探すのだけど、見当たらない。家の外をあちこち見ると室外機は何台かあるけど、全て違う。家を建てた時の現場監督がわかるはずだから、電話連絡するけど、忙しいのか、返事がない。もし壁をずっと通しているとなると工事はどうなるのかな?
その後、現場監督からの電話で二階からの真下、一階の外にあると思うって。いつも仕事場(織の)行く通路にありました。ホッとしましたが、よく見ると隠蔽配管なので工事がやりにくそうです。
そんなこんなで、まだまだエアコン問題は解決してません。(悲)
網かけ
毎日、暑い日が続いてます。家の中に居る間はまだ何とか過ごしているのですが、一旦、庭に出たりすると汗が滝にように出はじめて何度も顔を洗うということになり、その度に化粧水とか顔につけることが面倒になります。
鳥がブルーベリーの実を狙っていて、時々、まだ熟してないのにやって来る。たぶん、他の鳥に対するアピールなのだろう?これは自分のものだという。なので私も「私のものだ!」とアピールすることにしました。
こんなに大きな網目で良いのか?と思ったら、庭師さんが「鳥は網に引っかかると逃げることができないと知ってて、これで充分なんです。」って、そういうことなのだと納得でした。
いずれにしても収穫しようと思ったら、それなりに対策しないといけないのですね!
メダカはどう見ても1匹しかいない。メダカは初めての場所に入れられると飛び出してしまうそうです。ということで今のところ、ニホンメダカ1匹だけど、そのうち白メダカが加わるのを待ってます。
そうそう昨夕、庭に出るとハグロトンボが一羽、飛んでました。あれ!帰って来たの?と思ったけど、いつの間にかいなくなりました。写真に写す間もなく・・・
そんな庭模様でした!
やっと梅雨あけ
阪神間は梅雨が明けたようですね。徐々に暑くなって来ていたけど、昨日までの雨模様がすっかり消えて、今日は朝から日が射してます。顔を洗っても少し動けば、汗が止まらない。
ブルーベリーの実の色が赤くなって、ちらほら黒くなってるものもあるせいか、鳥が来る。いつもの鳥、ヒヨドリかイソヒヨドリのどちらかだと思う。昨年はほとんど彼らに食べられたので今年は網をかけて守るつもりだ。
ちょっと留守をするとどんどんツタがはいまわって、草木を覆ってしまってるので、この際、ツタを排除しようと、虫除けをあちこち塗り、蚊取り線香を腰にかけて、帽子を被って、ツタを引き抜いた。小さな庭なのですぐに終わったけど、根まで取れていないのでまたすぐに伸びて来るだろう。
前の日にはたくさんの蜂が飛び回ってたので、庭師さんが蜂取りを仕掛けてくれた。減ってるように思うが、水場で水を飲んでる、こんな姿を見ると蜂にもうしわけないと思う。
臼の雨水が溜まって蚊が増えそうなので、ニホンメダカ6匹を入れてもらった。今日、確認すると水草に隠れてるのか、1匹しか見つからない。でも楽しみが増えました。
こんな収穫もあります。これだけなんだけどね。
雨の合間に
2週間前、神戸に行ってました。しばらく居るつもりでした。けど、このところのコロナ感染の増加で但馬に帰った方が良い、息子は今の感染の上昇傾向はマズイとの判断でした。70歳過ぎた私たちは重症化するから当然のことだと思います。
ということで、ここに帰って10日間になります。毎日、家にこもる日々となりました。運動不足になってしまうので、雨雲レーダーの動きを見ながら、雨の降らない時を見つけて、自転車で走ってます。で、マスクをしていると蒸してくるので外すことが多いのです。
と!、声をかけられます。でも止まらないで「こんにちは!」と通り過ぎます。今は蜜を避けないといけないですからね〜 マスクをしてないと近寄ることができません。そんなわけで申し訳ないけど、通り過ぎてます。
田舎なので若い人以外は知り合いばかりです。でも最近は誰だっけ?と思うことが多くなりました。知り合いが年齢を重ねてしまって・・・ 私の場合、しばらくこの地に居ないことが多かったので徐々に年齢を重ねていくのを見るという緩やかな時間の経過がなく、ひとっ飛びに数年が経過しているので一瞬、誰だっけ?となってしまうことが多くなりました。多分、向こうもそうなんだと思います。
時に、ああ、この家の前で「元気にしてる?」などと声を掛けあった人はもういないと思いながら、通り過ぎることがあります。その時の笑顔を思い出し、ふっと淋しさを感じます。
この地に越してきて40年、私の人生の中で最も長い居住地になりました。子ども時代を過ごした岐阜時代よりもその後の東京や横浜時代よりも長くなりました。今、岐阜の実家があった場所に行っても全く知らない場所となってしまいました。いつの間にか住宅地に変わってしまった田畑や小山、子どもの頃、小川で遊んだ場所を見つけるのは至難です。私の記憶の中には今だに存在しているのですが。そしてそこで同級生の姿を見つけることも無理です。お互いに老けましたから。
私の住む但馬で大きく変化した場所は高速道路のインターチェンジ(IC)が設置されたところでした。この場所は広々とした大きな空間をもった田んぼでした。初夏には緑、秋には黄金の大地となる素晴らしい場所でした。その真ん中に立つと、ちっぽけな自分を感じて、悩みも吹っ飛ぶようでした。
但馬は山と山に囲まれた狭い空間に人々が暮らしてます。人々は山裾に家を立て、真ん中に農地という暮らしをしてきました。その中で最も広い空間だったのです。
この写真は道路で寸断された片側です。道路の反対側にも同じように農地が広がってます。高速道路は山に向かって伸び、先はトンネルになってます。下にはみやげもの店、食堂、コンビニなどが出来ました。
今でも広いとは思うのですが。明治時代に鉄道が通って、でもこの場所に駅は困る、大切な農地が失われないように駅は離れた場所に建てられました。線路は山裾に。そして移動手段が鉄道から自動車に移行する時代になって、結局、ここにICが出来ました。
最初は高速道路はここまででした。降りて来た車はしばらく、この地を潤しました。けど今、道はもっと先まで延長されて、通り過ぎる車が多くなりました。交通手段が変えていく、人々の暮らしの変化をかいま見ました。
今はコロナのせいで鉄道や高速バスの利用が減ってます。個人の車で移動したり、買物には行かず通販で家まで運んでもらうなどが多くなってます。それが続くのでしょうか?
今後、どうなっていくのか、今は先が読めません。
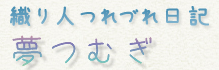






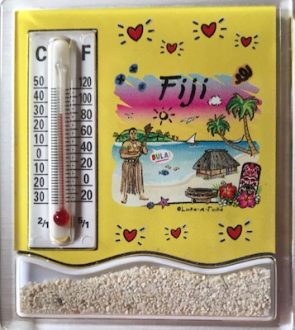













最近のコメント