健忘症
えっ!そんな・・・(絶句)
TVのドラマ「すぐ死ぬんだから」を観て、面白いとKindleで本を購入、深夜を徹して読み切って、友人に「面白いよ」って、SMSしたら、「私も観たよ!借りてるその本を返してないことを思い出したわ」って、なに?「それって内館さんのよね?」「そうそう前に面白いからって貸してくれたじゃない」・・・
全く記憶から飛んでるし、内容も覚えてなかった?!わけで。。その上、面白いからって、本を貸してるなんて!!
私が読んで想像した世界とドラマでの展開の違いかなあ?
健忘症が進んでる!!
そういえば、人の名前を覚えるのがもともと不得意だったけど、この頃、よく知ってる人の名前が出てこない。「えーと誰だっけ、ほら、・・・な人」と他の人に助けを求めて、やっとたどり着いたりする。
有名な人の名前の場合はGoogleで特徴をいろいろと入れて、見つけるなどなど・・(悲)
最もまずいのは漢字を書こうとするとぼうっと形が見えるけど、書けない。
たぶん大丈夫か?と医者にかかると「仕方がないですよ。老人性健忘症が進んでるわけだから」と言われるんだろうなって。(泣)
もうすぐ収穫
ということで漢字検定のアプリを入れて、どの程度、忘れているのか、小学5年生からトレーニング挑戦中です。5年生は楽勝!読みに関しては高校在学レベルまで来てるけど・・
けど、ゲームですからね〜 こういうのに嵌ると終わりがなくて、まずい!!
この頃は
暑い日が続きます。お盆を過ぎても。涼しくなる様子もなく、コロナ感染を避けて、外に出ないで過ごすのは皆、ストレスになっているかもしれない。
私はというと、このところ、過ごし方が変わってきてる。夜、寝るのは日がまわった深夜になってしまうので、朝、起きるのが遅い。
散歩に行く時間は夕方になる。まだ暑いし、ここは田舎なのに木陰が少ないので、買い物がてらに自転車に乗ることが多い。ただし最近は日没が18時半過ぎになってきてる。暗くなる前には帰って来たい。
家でふと見上げると照明のカサの埃が気になって掃除したり、冷蔵庫を開ける時、気になっている汚れを掃除したりと、意外とすることがあるものです。
もちろん、それらはついでにしてるんだけど・・
このところ、私の一日は朝晩の庭の水やり、何冊かの本を読むこと。読みながら、音楽を聴く。そして筋力が落ちないように適度な運動をする。それだけで1日が過ぎていく。
なんとなくだけど、ちょっと何かが足りないような・・・
薔薇の話
ある日、花屋の前を通った。そう言えば薔薇の花を飾りたいと思っていたことを思い出して花屋に入る。母の日の準備で忙しく働いている花屋さんでしたが。「薔薇の花をください」と言うと、「薔薇ですね」といくつかの薔薇の花を指して「どれにしますか?」と聞かれたので「香りの良い花がいいです。」と応えた。
ところがガラスケースの薔薇の匂いを嗅ぎながらの「香りのあるのはないですね」と言うのです。確かにどの花も匂いはない。仕方がないので、それでもいくつか買って帰りました。
花を生けながら、あれ!と思ったのです。薔薇=棘、という、あの茎を持った時の痛みが全くなかったのです。そういえば棘はどうなの?と茎を見て、どこにあったっけと探すのだけど…どの花にも棘がなかったのです。なんとなく気抜けしてしまいました。
せめて香りは残してほしかった!!
香りがある薔薇を求めたい!
手紙
日本から、手紙が届いた。久しぶりに読む手紙。
昨年、亡くなった友人を偲んで4月3日に昔の仕事仲間が集まったのですが、
私はニュージーランドに居て参加できなかったのです。企画した友人が写真
を同封してくれました。
もう45年ほど昔の仲間ですが、10年ほどの間隔で集まってます。
仲間と言っても私たちを導いてこられた先生と奥様、もう一人、小児精神
科医の先生、どちらも最も尊敬する方々です。も、参加されてます。遠い昔に
なりましたが、大学を卒業して初めて仕事をした場所でしたが、大切なこ
との基本を教えていただきました。そこは私にとっては学びの場でした。
偲ぶ会、写真の友人は凛として素敵でした。大学時代からの親しい友人でした。
うんと長い彼女との年月を思いだします。それなのに、私は彼女が病気になって
以来、いろんなことが重なって会うこともなく、彼女との最期のお別れにもニュ
ージーランドに居て、それを知った時、すでに一週間過ぎてました。
闘病は辛いけど、必ず治るって信じているの!と電話で話してくれた彼女だった。
写真の彼女はこちらをじっと見つめてます。ああ、会えないんだなあ!と思う。。
でも、そのうち私も行くからね!って、言える歳になった…思うのです。
もう一枚の写真は偲ぶ会に参加された全員が写っているものでした。
みんな「変わらないわね〜」と言いあったそうですが…
写真のみんなはすっかり歳を重ねてます。きっと実際に会ったら、声とか雰囲気とか、
醸し出すものが変わらないのでしょうね。
私も会いたかったです。私が日本に帰ったら、また集まりましょうと、
言って下さったみたいで…楽しみが増えましたが…
夢
今朝、妙な夢を見た。夢の中では自分の家だった。けど起きて思い出すと知らない場所だった。夢って不思議なものだけど。。。登場する人も知らない人だったり、知っていても全く夢の場につながらない人だったりする。
今朝の夢もそうだった。この10年に会った人とうんと昔からの人、全く知らない同士なのに夢の中ではお互いに知り合ってるように話をしている。
なにかな?私の深層心理のところが見えているのか?不安を感じてしまった。
つい最近、父の姉、伯母が他界した。それを知らなかった。ごくごく身内で見送ったらしい。伯母は私が子どもの頃から50年、父が亡くなった後も母と一緒に暮らしていた。我が家では母が父親役で伯母が母親役だった。ことある毎にまるで母のようにいろいろしてくれた。おふくろの味も伯母だった。子育てで大変な時期にも助けてくれた。
ちょうど今の私の年代だったのかなあ。伯母は隣に、母は後ろに。
伯母の料理はとても美味しかった。83才だったかな、もう料理を作るのはやめたい、母も仕事をやめると言い出して、それぞれが違う場所に移ってしまった。母も伯母も実の姉妹ではないけど、50年一緒に暮らすと最も近しい間柄になっていた。で、私の家にふたり一緒にやってきて長く逗留していた日々もあった。
ある年、伯母は足がむくんだ状態でやってきた。以来、心臓が悪くなり、我が家にも来れなくなり、なかなか会えなくなってしまった。母も伯母も90才を過ぎていた。ふたりは会えない時には電話で話していたがどちらも耳が遠くなって電話でも話すことができなくなり。。。そして、ふたりとも、車椅子の生活になってしまった。
伯母が亡くなったことを母に話すと、一瞬、驚きの表情をした。けど、そんなに悲しいようでもなく、受け入れている。同じ墓に入るつもりなのでまたそこで話をするらしい!母も生死の狭間を行ったり来たりして、今は元気だがいつどうなるか、わからない。だから受け止め方があっさりなんだ。。と書いていたら、弟からメールが入って、昨日、母が低血圧でお風呂で意識を失ったらしい。今は元気だとか。
伯母にはいつでも会えると思っていた。けどついつい後回しにしてしまった。見送れないと大きな悲しみは襲ってこないけど、じわりじわりと思い出す。その度に別れの寂しさを感じる。
夢には伯母は出てこなかったけど、なぜか夢から覚めた時に思い出す。
幸せ感
歩くには無理だと曲がりくねった細い坂道をタクシーで宿に着いた時、辺りは真っ暗になっていた。美味しいとはとても言えない夕食をすませ、大浴場には行かず古いユニットバスに入る。この時期の京都は観光シーズンで11月に入ってから宿を取るのは難しい。ちょっと不便だけど、まあ良いかと予約した宿、今時、めずらしくテレビもない部屋だった。次の作品のために草稿を描くつもりだったけど、暖房を入れて暖かくしたら睡魔に襲われてしまった。
早く寝たせいで5時半に目覚めてしまった。外はまだ暗い。うとうとしているうちに徐々に明るくなってきた。と。。
あれー!これは!?と窓の外に現われた光景にびっくり!窓を開けて、身を乗り出す。
思いがけない光景だった。急いで着替えて、フロントに行く。
この景色がよく見える場所に行きたいのだけど、どう行くのが良いの?と訊ねると
三階の非常口から行くのが良いでしょうと。
その非常口を開けるとまたまた予期しない光景が待ってました。
これって能舞台ではないか。どういうことなんだろう?
この宿、どう見ても洋館なんだけど、妙なミスマッチに首を傾げながら進む。
このガラスの波打つような状態、かなり古い。。けど、能舞台が造られた後に入れたような気もする。
能舞台の向こうに美しい樹々が見えている。そのまま進む。
この能舞台の家屋のための門があり、そこから能舞台のある玄関までの通路に出た。
裏山を背にした空間に広がる樹々の美しさに息をのむ。
足元にも。。。
見上げて葉の色の重なりにうっとり!静かな時がながれていく。
もういちど庭に戻ると能舞台の庭に入る手前に下に向かう道がある。
進むと外待合の腰掛があり、その目線の先に茶室があった。
能舞台の庭もよく手入れしてあった。ここの庭もそうだ。使われているのだろう。
茶室の先を降りるとそこは私の部屋から見えた場所だった。二階になる。こちらの施設はどうみても洋館なのだ。
フロントに行き、このミスマッチについて訊ねた。
能舞台は秀吉の豊公三百年祭の時(明治時代)に建てられたものでそれが廻り回ってここに。個人所有だったけど、売りに出された時に地続きなので購入し、茶室も能舞台も使われているということだった。あのガラスも三百年祭以後に入れられたという。そういうことかと納得する。
せっかく早起きしたので周囲の散歩に出かけた。
曼殊院が近くて、その周囲は朝の散歩に来た人、カメラを担いでいる人が疎らにいるだけでまだ観光客がいない。
なかなかいい散歩道だった。
曼殊院の参道
曼殊院の前の神社から見えた景色
歩きながら、遠くを見れば、向こうの山が。。京都は山に囲まれているのだったと思う。
宿に帰って正面横から見るとまさに裏は山。そして洋館。
急に冷え込んだおかげで思いがけない美しさに浸れてとても幸せな朝だった。
家を建てるということ
家を建てかえることにした。息子夫婦と暮らしはじめて3年半、そろそろ二世帯住宅にしようかということになった。年代の差、価値観の違いでお互いにストレスを感じるよりは、同じ敷地内に二家族が分かれて住むという選択をすることになった。
家を建てるということ。簡単ではない。もちろんお金も要る。できるだけシンプルでいいのだが、始めると持っていたものを捨てて良いのかという思いにかられる。消費社会に生きているしっぺ返しがもろにくる。贅沢な暮らしをしていたものだと思う。基本になる家そのものは新築だけど、家具などは今までのものを使うということにしているが、その選択が難しいのだ。
ずっと使ってきた家を二つに分けるのだから、今までよりも狭くなる。気に入って買ったものもばかりのはずだから、捨てることに抵抗がある。どうしても収まりきれない。今や捨てることも美徳のように言われる時代、よく考えるとやはり何か間違っているように思える。
消費社会にすっかりのせられて、ついつい買ったものが過剰にある暮らしなのだ。捨てることは当たり前になったけど、本当にそれで良いの?と思ってしまう。
便利な暮らし、過剰にある物、それに囲まれていたこと。今もいること。
そこをしっかりと自分に中で整理しないと実は家を建てることが前に進まないということに気づいた。
地震と原発事故のあと、原発をなくすために私は何ができるのか、考えた。まずは電力を湯水のように使う今までの暮らしを見つめ直すことに他ならない。具体的に言えば、食洗機が要るのか、便座は暖かい方が良いのか、床暖房が良いのかという。。。それって、豊かなのか??
消費することを抑える。暮らしそのものを今一度、見直す。
家を建てかえるということ。それはとても大変な作業であり、自分の暮らし方、生き方を問い直す重要な機会を与えられたのだと思い、なかなか前に進まない。
カウンセラー?
子どもと共にいること。
私は遠い昔、保育の現場で働いていた頃、同僚から、あなたは「何も構えず、こどもに入っていけて良いわね」と言われたことがあります。たしかに初めて会う子どもを受け入れる時にどう受け入れようとか、など考えたことがなかった。
何の抵抗もなく子どもと共にあるから。いつだって子どもの心に触れることは難しいことではなかった。それに子どもの遊びの発展に付き合うのは楽しかったのです。若かったから、全身で臨んでました。
それから時が過ぎ去って、自分の子どもも成長したある日、そんな話を友人にした。そうしたら、その友人が言うには子ども好きのはずなのに私が他の子どもがいても全く興味を示さないし、一緒に遊ばないのはどうして?と。子どもが好きではないのではと。
私は子どもと自分が遊ぶことを目的に子どもに接していないのです。保育者は子どもの全てを受け入れる立場にあって、その間、その人の人生と向き合っています。遊びは子どもの成長にとって、とても重要です。遊びが全てなのかもしれません。遊びをとおして、自発性、積極性、集中力、探究心、社会性などを身につけていくのです。それはこちらのペースで行われるものではなく、子どもが決めていくものなのです。それを受け入れ、見守り育てるのが保育者の立場なのです。
だから自分からは行動しないし、遊ばせることもないのです。求められれば、自然に入り込むことができる体制は常にあるのですが。必要がないところでは何もしないのです。それは常に変わらない私の姿勢です。
自分の孫にも同じです。可愛いから、いろいろ遊具も揃えていますが、遊んであげることはしません。でも孫は私のところに来るのが好きで、特に少し精神的に不安定になるとやってきます。しばらくいるとすっかり笑顔になって帰っていきます。特に何をしているわけではないけど。。
そういった姿勢からか、なぜかわからないけど、私は不安な人の心に抵抗なく入り込んでしまうことがあります。そして、いつのまにかカウンセラーになっている自分を発見する時があります。それを長い間、すっかり忘れてました。つい最近、会った人の心に入って、そうなっている自分に気づいて思い出したのです。
本来、もっている自分の性格?を再確認しました。
カウンセラー!?
でも私はその人と一緒に心を動かすので心の消耗が激しく仕事にしたら向いてないのです。
孫が求めた時に受け入れる、おばあちゃんカウンセラーが適しているのかもしれません。
親友
ずいぶん長い間、ゆっくりと話すことがなかった友達。
大学に入って、最初の出会いはもう覚えていないけど、どういうわけか、とても気があって、いつも一緒だった。青春時代の多感な時期、話すことがいっぱいあって、毎日、出会っていても尽きることがなかった。読んでいる本の話、好きな詩集のこと、恋の話などなど、声をだして話すとまずい授業中には筆談したりしていた。
何が原因だったか覚えていないけど、喧嘩したことがあって、授業中、違う場所に座る一週間があった。他の友人達がヤキモキして気にしたほど、仲が良かった。そんなこともすっかり忘れていた。遠くに離れてしまうと会う機会が減って何年もお互いの空白の時代ができてしまった。
久しぶりに会って食事をしながら、最近のお互いの話をした。
同級会などで同級生に会うと昔はこんなことがあったとか、その頃はどう思っていたとか、今は何をしているといった表面的な話で終わることが多いし、次にまた会おうと別れても次はないことが多い。
親友というのは何年も会ってなくても、会うとお互いの琴線に触れる話にいつのまにか入り込んでしまうらしい。あの青春の多感な日々を共にしたからなのか、それとも同じ波長のせいなのか。彼女の話は面白かった。年を重ねてこそ、わかる人生の深み、ふっと肩の荷が降りるようないい話を聞いた。
若かった時代、彼女はバイオリンを弾いていた。今はチェロにすっかり嵌っていると前に会った時に聞いた。とてもナイーブな人だから、チェロの音に惹かれたのはなんとなく解る。「すごく落ち着くの」って。
彼女に会って、私自身、忘れていた何かを取り戻した気がする。最近、ふと我に返って自分をみつめていた、ちょうど良いタイミングでもあって。。。
彼女も楽しかったらしい。今度は彼女達夫婦と会う約束をした。私と彼女と彼は同じサークル仲間だった。(^-^)
親友って、いい!
あの日あの時…
落ち葉を踏む音。カサカサ!「ほら!カサカサって音がするでしょう。面白いね!」こんもりと積もった落ち葉がどこまでも広がる。息子に声をかけながら、じつは私が楽しんでいた遠い昔を思い出して、公園に行こうと思い立った。
すっかりビルばかりになった通りを歩いて、坂を下り、踏切を越えて、信号を渡る。昔と同じ道。公園の入り口を入ると整備された公園内、大きな道と小道がいくつかある。あの頃はこんな大きな道はなかった。高低差のある広い原っぱに近かったような気がする。
くるりと見回すと目に飛び込んできたのは林。樹々に包み込まれたような感覚を覚える。少し気分が落ち込んでいたのだが樹々のオーラに包まれて消えていくのを感じた。
道を登っていく。そこにはまた違う景色が現われた。
そしてもう少し進むと、かがんで写真を撮っている人がこの構図が良いと勧めてくれた。
進むごとに違う種類の樹々が現われる。
それにしても35年以上、こんなに木は太く大きくなるんだ!
あのカサカサという音のする場所はどうなっているんだろう?広葉樹の多い林のはず。
公園内はかなりの広さなので当時まだ2歳だった息子を連れて行くとその場所まで一時間はかかった。考えたら、その子も今はお父さん。大きくなったこと。
今、園内には自転車道もあって自転車も貸している。
自転車練習用に作られた場所もある。
そこを過ぎたところに。
落ち葉も、モグラの穴も、ありました。
昔に比べたら、少ない落ち葉です。あの頃は靴が入り込んでしまうような深さがあった。今はそんなことはなかったけど、この場所に間違いないのです。すっかり整備されて、遊歩道ができて、落ち葉を踏むようなこともない。落ち葉を抱えてバラまくこともないだろう。小道を自転車に乗った子供達が走り抜けていく。
遠い日に思いをよせて、なんだか、あの時代は良かったような気がしました。
そこを後にして進む。
まだまだ一周してないのです。ちょうど半分きたところですから。
くるりと公園の端を回っているので途中で公園の真ん中を写してみる。
といっても全てではなくて、ほんの一部ですが。
正面の入り口に近くなると2〜3人組の若者達が何組も、漫才かなあ、それとも舞台かなあ、大きな声で練習している。ほとんど男の子なのが不思議。
その近くには黄色い世界。
公園の正面付近は都会化していて、写真を撮る気にならず。。。ベンチにも芝生にも人が多い。忘年会?まさか?何人か集って楽しく賑やかなグループも。犬の散歩、ジョギングなどなど。人って群れるんですね〜。
これ!洋風な。。。
その場を過ぎると葉が落ちた樹々が。
「ここは紅葉が終わってるのね!」という会話が聞こえる。
この木は木を守る人々によって生き返った木だと説明があった。
上の写真の正面に写ってる小道を入ると最初の場所に戻った。所要時間2時間。
その道の途中で出会った人は「この構図、良いよ」と教えてくれた人だった。ニコニコと声をかけられのだが外国語でよく解らなかったのが残念。
代々木公園!
昔とは変わってしまったけど、散歩コースには良い!
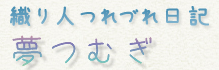
































最近のコメント